おはようございます!
今日も、えほん文庫のブログを読んでくださって、ありがとうございます
今日の午前中は、えほん文庫で、「絵本の読み語り はじめの一歩講座&紙芝居レクチャー」を、ご依頼いただいた読み聞かせサークルさんの貸し切りで行う予定です♪
今回は、特別に紙芝居に関しては、友人のOさんが担当してくれます!
Oさんは、紙芝居にとても詳しい方で、私も、基本の読み方をOさんに教わってから、皆さんの前で自信を持って読めるようになりました(*'▽')
紙芝居舞台の開き方や、紙芝居のめくり方、自分の立ち位置など、基本となることを教えていただきました!
(2年前に、えほん文庫で開催した、「第1回紙芝居フェスティバル」で、レクチャーしてくださった方です)
また、本日午後3時~5時は、月に1回の「木曜日のオープン日」になっていますので、どうぞお気軽にお出かけくださいませ(^O^)





さて、ブログ「(仮題)我が家の次男はダウン症」を書いている方が、「やってみよう!プロジェクト」を立ち上げ、
ダウン症の告知を受けたママたちの手記を自費出版することを、呼びかけたところ、
全国、また世界から手記が集まり、87名分の手記がまとまり、このたび完成いたしました(*'▽')

私も手記(リポート)を提出させていただいた一人です
締め切りは5月末まででしたが、私が多めに注文しましたので、お早目にご連絡いただけたら、予約のない方にもお渡しできます。
(ご予約いただいた方には、順次ご連絡しているところです)
また、全国紙でも取り上げられたため、各地から注文が集まっているようで、増刷の見込みですので、
えほん文庫で受け渡しできる方は、ご注文をこちらでお受けすることもできます。
冊子は 1冊500円です。
☆先日放送された「出生前検査は何をもたらすのか?」シリーズはご覧になられましたか?
NHKハートネットテレビ 「第1回命の選択をめぐる模索」
「第2回どうしたら産み育てられますか?」
アメリカでは、医療従事者(告知する人)と、ダウン症児を育てている親御さんとの話し合いが持たれているのですね。。。
告知する医師が、家族の思いを理解し、発言(告知)できるよう、勉強会を開いている様子が放映され、
実際にダウン症の告知を受けた方には、ダウン症の子供を育てている親御さんと引き合わせるような仕組みも作っているようです!
告知する時にサポート体制が出来ているのと、ないのでは、受け取り方が全く違うと思うのです。
私も、微力ながら・・・告知されたばかりのママに寄り添うサポートが出来たら嬉しく思います♪
まずは、「やってみよう!プロジェクト」で自費出版した、この冊子が、産科に設置され、医師たち、そしてママたちの手に届くところに置いていただけたら、と願っています(^O^)/
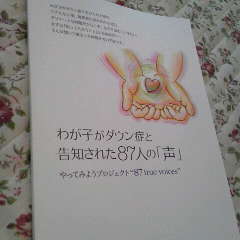
 そして、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、、、なんと
そして、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、、、なんと このあたたかい表紙のイラストは、えほん文庫のすべてのイラストを描いてくださった「るっこら」さんが担当されました
このあたたかい表紙のイラストは、えほん文庫のすべてのイラストを描いてくださった「るっこら」さんが担当されました
私が、手記を応募する時に、自己紹介のつもりで、えほん文庫のホームページをお教えしたところ、手記冊子の主宰のママが見てくださって、
えほん文庫のホームページや、ブログの「イラストが可愛いですね!」とコメントくださったので、描いてくださった「るっこら」さんをご紹介したところ、
制作中だった手記冊子の表紙の絵をお願いすることになったのでした(^O^)/
締切が迫っての依頼だったのですが、、、るっこらさんはお忙しい中、2日ほどで、イラストを描き上げてくださり、本当に有難く、大変恐縮いたしました(>_<)
(全部で9枚ものイラストを描いてくださった中から選ばれたのが、表紙の絵です)
あたたかい想いがこもったイラストが、全国のダウン症の子供を育てているママたちの想いを代弁してくれているようにも感じます。
るっこらさん、本当にありがとうございました!るっこらさんのブログは→こちら☆☆☆です
私は、購入した この手記(冊子)を、私が ごうちゃんを産んだ病院に持っていく予定です。
「赤ちゃんに、ダウン症の疑いがある!」と告知された、6年前のあの夜。。。
多くのママたちが、新しい命の誕生で幸せに満ちていた あの産科病棟で、
世界中の不幸をすべて背負ったように思え、一人ぼっちだった私。。。あの時の私に、この冊子を届けに行ってきます!
私は、ダウン症児を育てている家庭が、どんなに幸せに満ちているのか、、、
というより、、、ごくごく普通に暮らしている!ということを、
ごく自然に社会に広めていけたら、、、と願っています
☆今後、産院、助産院などに置いていただけるよう交渉していくつもりですので、ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、お申し出いただけたら有難いです。
今日も、えほん文庫のブログを読んでくださって、ありがとうございます

今日の午前中は、えほん文庫で、「絵本の読み語り はじめの一歩講座&紙芝居レクチャー」を、ご依頼いただいた読み聞かせサークルさんの貸し切りで行う予定です♪
今回は、特別に紙芝居に関しては、友人のOさんが担当してくれます!
Oさんは、紙芝居にとても詳しい方で、私も、基本の読み方をOさんに教わってから、皆さんの前で自信を持って読めるようになりました(*'▽')
紙芝居舞台の開き方や、紙芝居のめくり方、自分の立ち位置など、基本となることを教えていただきました!
(2年前に、えほん文庫で開催した、「第1回紙芝居フェスティバル」で、レクチャーしてくださった方です)

また、本日午後3時~5時は、月に1回の「木曜日のオープン日」になっていますので、どうぞお気軽にお出かけくださいませ(^O^)





さて、ブログ「(仮題)我が家の次男はダウン症」を書いている方が、「やってみよう!プロジェクト」を立ち上げ、
ダウン症の告知を受けたママたちの手記を自費出版することを、呼びかけたところ、
全国、また世界から手記が集まり、87名分の手記がまとまり、このたび完成いたしました(*'▽')

私も手記(リポート)を提出させていただいた一人です

締め切りは5月末まででしたが、私が多めに注文しましたので、お早目にご連絡いただけたら、予約のない方にもお渡しできます。
(ご予約いただいた方には、順次ご連絡しているところです)
また、全国紙でも取り上げられたため、各地から注文が集まっているようで、増刷の見込みですので、
えほん文庫で受け渡しできる方は、ご注文をこちらでお受けすることもできます。

冊子は 1冊500円です。
☆先日放送された「出生前検査は何をもたらすのか?」シリーズはご覧になられましたか?
NHKハートネットテレビ 「第1回命の選択をめぐる模索」
「第2回どうしたら産み育てられますか?」
アメリカでは、医療従事者(告知する人)と、ダウン症児を育てている親御さんとの話し合いが持たれているのですね。。。
告知する医師が、家族の思いを理解し、発言(告知)できるよう、勉強会を開いている様子が放映され、
実際にダウン症の告知を受けた方には、ダウン症の子供を育てている親御さんと引き合わせるような仕組みも作っているようです!
告知する時にサポート体制が出来ているのと、ないのでは、受け取り方が全く違うと思うのです。
私も、微力ながら・・・告知されたばかりのママに寄り添うサポートが出来たら嬉しく思います♪
まずは、「やってみよう!プロジェクト」で自費出版した、この冊子が、産科に設置され、医師たち、そしてママたちの手に届くところに置いていただけたら、と願っています(^O^)/
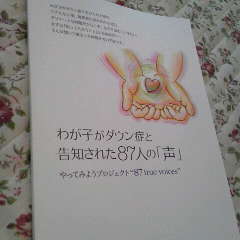
 そして、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、、、なんと
そして、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、、、なんと このあたたかい表紙のイラストは、えほん文庫のすべてのイラストを描いてくださった「るっこら」さんが担当されました
このあたたかい表紙のイラストは、えほん文庫のすべてのイラストを描いてくださった「るっこら」さんが担当されました
私が、手記を応募する時に、自己紹介のつもりで、えほん文庫のホームページをお教えしたところ、手記冊子の主宰のママが見てくださって、
えほん文庫のホームページや、ブログの「イラストが可愛いですね!」とコメントくださったので、描いてくださった「るっこら」さんをご紹介したところ、
制作中だった手記冊子の表紙の絵をお願いすることになったのでした(^O^)/
締切が迫っての依頼だったのですが、、、るっこらさんはお忙しい中、2日ほどで、イラストを描き上げてくださり、本当に有難く、大変恐縮いたしました(>_<)
(全部で9枚ものイラストを描いてくださった中から選ばれたのが、表紙の絵です)
あたたかい想いがこもったイラストが、全国のダウン症の子供を育てているママたちの想いを代弁してくれているようにも感じます。
るっこらさん、本当にありがとうございました!るっこらさんのブログは→こちら☆☆☆です
私は、購入した この手記(冊子)を、私が ごうちゃんを産んだ病院に持っていく予定です。
「赤ちゃんに、ダウン症の疑いがある!」と告知された、6年前のあの夜。。。
多くのママたちが、新しい命の誕生で幸せに満ちていた あの産科病棟で、
世界中の不幸をすべて背負ったように思え、一人ぼっちだった私。。。あの時の私に、この冊子を届けに行ってきます!
私は、ダウン症児を育てている家庭が、どんなに幸せに満ちているのか、、、
というより、、、ごくごく普通に暮らしている!ということを、
ごく自然に社会に広めていけたら、、、と願っています

☆今後、産院、助産院などに置いていただけるよう交渉していくつもりですので、ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、お申し出いただけたら有難いです。



150.png)




 at 2013年06月27日 14:43
at 2013年06月27日 14:43














ちなみに・・・。
5月末で締め切ったのは、私が業者への「発注部数を読むため」でした。
なので、「購入してくれる人の注文締切」ではないのです~
なので、ご注文はまだまだ受け付けております☆
そのへん、誤解されている方が多いのでまた記事にしますね!
ほんと。綺麗なイラスト。
みんなまずここで、癒されるみたいです。
そんなレポが寄せられております。
ご協力に感謝です!
ありがとうございました。